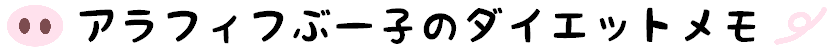発酵食品といえばヨーグルトや納豆、味噌、醤油、甘酒などが定番ですが、最近は手作りする人も増えてきました。
腸活を効果的にするには、いろいろな種類の発酵食品を摂るのがおすすめです。
今日は発酵食品の種類や、発酵に使われる菌種や効果についてメモします。
毎日の発酵ライフにご活用ください♪
発酵食品には何がある?
発酵食品でよく話題になるのは納豆や味噌、甘酒、チーズやヨーグルトですが、無意識のうちに食べている発酵食品も多くあります。
たとえば味噌汁に使われる発酵食品は、味噌だけではなく出汁に使った鰹節も発酵食品。
そして納豆や漬物にかけた醤油も発酵食品ですし、日本酒やワインなども発酵食品です。
身近な発酵食品をまとめてみると
|
穀類・豆類 |
パン 納豆 テンペ 豆腐よう 腐乳 臭豆腐など |
| 野菜 | 漬物(ぬか漬け すぐき 柏漬 奈良漬け べったら漬け キムチなど) ピクルス ナタデココ ザーサイ メンマ ザワークラウト バニラなど |
| 魚肉 | サラミ ペパロニ 熟成肉 鰹節 発酵昆布 塩辛 くさや なれずし アンチョビなど |
| 乳製品 | チーズ ヨーグルト 発酵バター サワークリームなど |
| 飲料 | 日本酒 ビール ワイン 焼酎 泡盛 ウイスキー ブランデー シードル マッコリ 紅茶 烏龍茶 プーアール茶 甘酒など |
| 調味料 | 醤油 味噌 酢 本みりん 麹 魚醤 ワインビネガー ウスターソース ナンプラー 豆板醤 コチュジャンなど |
この他にも「いぶりがっこ」や「どぶろく」など、その土地ならではの伝統的な発酵食品がたくさんあります。
発酵に使われる主な菌類

発酵に使われる主な菌種には乳酸菌、酢酸菌、納豆菌、酪酸菌、酵母菌、麹菌、カビ(麹菌以外)などがあります。
発酵食品は1種類の菌で作られるものもあれば、味噌や醤油、ぬか漬けなどのように数種類の菌で段階を経て作られるものもあります。
乳酸菌
ヨーグルト、漬物、キムチ、醤油、味噌など

身近な菌種で、ヨーグルトメーカーなどで手作りしやすい発酵食品。
糖類を分解して乳酸を作り出します。
乳酸菌には動物性乳酸菌と植物性乳酸菌があり、植物性乳酸菌は胃酸に強く生きたまま腸まで届くといわれています。
もちろん死滅しても腸内の常在菌のエサとなるので、腸によい効果が得られます。
酢酸菌
酢、ワインビネガー、バルサミコ酢、ナタデココ、紅茶キノコ(コンブ茶)など

アルコールやブドウ糖から酢酸を生成します。
疲労回復や血糖値とコレステロールを抑制する効果が期待できます。
関連記事
納豆菌
納豆を作る微生物。

枯草菌の一種で、稲わらなどに生息しています。
発酵の過程で主にプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)、アミラーゼ(でんぷん分解酵素)、ナットウキナーゼ(血栓溶解酵素)を生成します。
老廃物の排出を促して肌の潤いを保つ作用がある他、血栓防止効果や血圧降下、血行促進に効果が期待され、心筋梗塞や脳梗塞の予防につながります。
また納豆菌は胃酸に強く生きたまま腸まで届くため、整腸効果も期待されます。
酪酸菌
チーズやぬか床に生息する微生物で、胃酸に強く生きたまま腸まで届きます。

嫌気性菌で酸素がないところで繁殖します。
ぬか床を毎日混ぜるというのは、底の方に生息する酪酸菌と上の方に生息する好気性の産膜酵母を入れ替えるためです。
酪酸菌は食物繊維を乳酸菌などの善玉菌のエサに作り変える働きがあるため、プロバイオティクスと呼ばれ、注目されています。
関連記事
→ ぬか漬けの効果効能まとめ!野菜の芯や皮なども捨てずにぬか床へ!
酵母菌
パン、酒、醤油、味噌など

自然界の空気中や土壌など、あらゆるところに生息し、糖類からアルコールと炭酸ガスを生成します。
ビール酵母、清酒酵母など、いろいろな種類の酵母があり、ビールや日本酒、ワイン、焼酎、パンなどが作られています。
酵母菌は熱に弱く、流通しているものは加熱処理のために酵素などは失活しています。
加熱処理されていないものは、冷蔵で販売されているものや蔵元から直接購入することで手に入ります。
関連記事
→ 太りにくいパン・太りやすいパンはどんなパン?種類や食べ方まとめ
麹菌(国菌)
甘酒、塩麹、味噌、醤油、みりん、酢、日本酒、鰹節など

麹菌は日本の発酵食品になくてはならない微生物で、原料のデンプンを糖に分解し、100種類を超える酵素を生成します。
麹菌の場合は麹菌そのものの発酵よりも、この酵素の働きによる「糖化発酵」が重要。
デンプンを分解してブドウ糖を生成した後、乳酸発酵や酵母発酵、酢酸発酵と引き継がれます。
関連記事
→ 塩麹は手作りで!簡単にできる基本の作り方と美味しく作るポイント
→ 体にいいのはどれ?味噌の種類や効能の違いと選び方や保存法まとめ
→ 鰹節にも種類がある?種類の違いや味の違い、栄養や選び方まとめ
カビ
テンペ、ブルーチーズなど

麹菌以外のカビとして、クモノスカビと青カビがあります。
クモノスカビはテンペ菌と呼ばれ、インドネシアの納豆と呼ばれる「テンペ」が作られています。
テンペは納豆のような臭いや糸を引くことがなく、揚げたり炒めた後に味付けされて屋台などで売られています。
日本でもスーパーで見かけるようになりました。
青カビはブルーチーズに添加するカビで、このカビから抗生物質の「ペニシリン」が発見されています。
チーズの種類によって、ロックフォール(フランス)、ゴルゴンゾーラ(イタリア)、スティルトン(イギリス)があり、世界3大青カビチーズと呼ばれています。
その他の発酵
イカの塩辛やめふん、アンチョビなど

発酵食品には、微生物が存在しないものもあります。
魚などが自身の持つ酵素で糖質やタンパク質、脂質などに分解されて柔らかくなる「自己消化」による発酵で、腐敗を防ぐために塩漬けされています。
自己消化による発酵を応用したものに「熟成肉」があります。
熟成させることで柔らかくなり旨みもアップするので人気が高まっていますが、発酵させるには専門の知識が必要です。
発酵食品の効果

発酵食品とは、微生物などの生命活動によって食品が変化すること。
風味が加わって美味しくなるだけでなく、さまざまな効果が期待できます。
腸内環境の改善
発酵食品には乳酸菌などの善玉菌が豊富に含まれているため、腸内環境を整える効果が期待できます。
腸内環境が悪いと便秘や下痢の原因になるだけでなく、悪玉菌が有害物質を作り出して腸から吸収され、栄養吸収が悪くなったり肌荒れなどの原因になります。
また免疫力も落ちて、風邪をひきやすくなったりアレルギーの悪化にもつながります。
栄養が豊富
発酵することで栄養素が変化したり新たな栄養が生み出されたりします。
ぬか漬けは本来の野菜の栄養に加え、米ぬかのビタミンや乳酸菌も一緒に摂ることができます。
保存性が高まる
発酵食品はもともとは保存食として作られたものが多くあります。
伝統食品である漬物や味噌などは、発酵することで微生物やアルコールが腐敗菌など他の菌の繁殖を抑えるため、長期保存が可能になります。
発酵食品まとめ

いろいろな発酵食品をご紹介しましたが、無意識のうちにいろいろな発酵食品を口にしていたのではないでしょうか。
市販されている発酵食品は品質を保つために発酵止め(火入れなど)をしているものがほとんどで、栄養はありますが酵素は残念ながら失活しています。
甘酒や塩麹など、簡単に手作りできるものもあるので、酵素たっぷりの発酵食品、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。